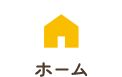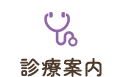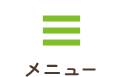赤ちゃんや子どもの発熱が続く
 赤ちゃんや小さなお子様は室温や重ね着により一時的に体温が上がることがあります。元気があるようなら、室温を下げる、薄着にするなどして30分後に再度体温測定をしてみましょう。体温が37.5度以上の状態が続く場合は「発熱」と判断します。
赤ちゃんや小さなお子様は室温や重ね着により一時的に体温が上がることがあります。元気があるようなら、室温を下げる、薄着にするなどして30分後に再度体温測定をしてみましょう。体温が37.5度以上の状態が続く場合は「発熱」と判断します。
生後3か月未満の赤ちゃんは、まだお母さんからもらった免疫が体内に残っているため、通常は風邪などの感染症にかかりにくいとされています。そのため、この時期の発熱は重い病気のサインかもしれませんので、早めの受診をおすすめします。お母さんからの免疫は生後6か月ごろになくなるため、そのころから発熱しやすくなります。特に保育園や幼稚園に通い始めたばかりのお子さまは、ウイルスや細菌に触れる機会も増え、感染による発熱を繰り返すことが多くなります。
発熱のパターンや、その他の症状の有無などを医師に伝えることで、正確な診断と必要な検査・治療ができます。「なんとなく心配」「いつ受診すべきか迷う」といった場合でも、お気軽に当院へご相談ください。
受診が必要な子どもの発熱症状をチェック
 以下のような場合には、お早目に当院にご相談ください。
以下のような場合には、お早目に当院にご相談ください。
- 生後3か月未満の発熱
- 呼びかけても反応がない
- ぐったりして元気がない
- 水分を摂れない、尿が少ない
- 顔色が悪い
- 呼吸が浅い・早い、息苦しそう
このような症状がない場合でも、3日以上発熱が続く場合は受診をおすすめします。
震えているのは寒気から?
けいれん?
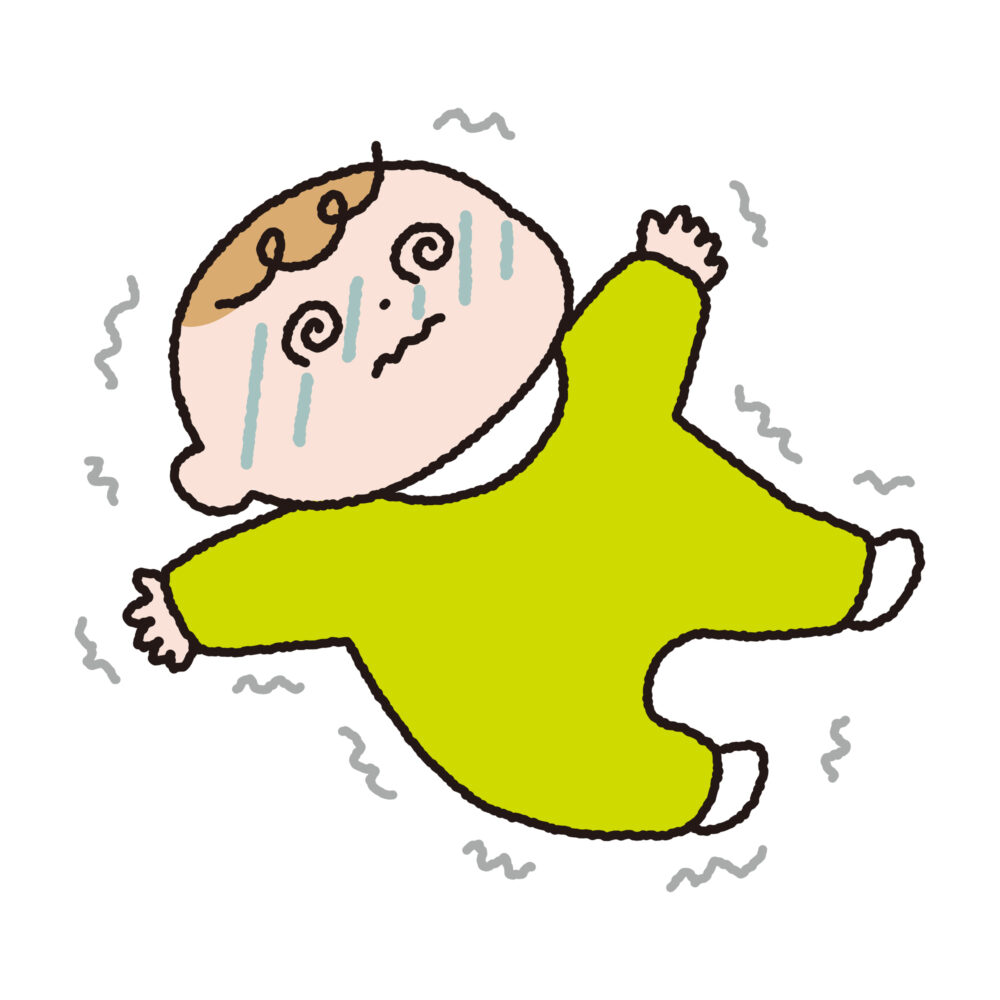 お子さまが急に震えだしたとき、「寒いのかな?」「けいれんかも?」と心配になることがあると思います。
お子さまが急に震えだしたとき、「寒いのかな?」「けいれんかも?」と心配になることがあると思います。
感染症の初期には、体温が急に上がる際に、寒さを感じたり身体が震えたりすることがあります。これは、体が病原体に対抗しようとする正常な反応で、体温はすでに高いのに「寒い」と訴えることもあります。
一方で、熱性けいれんなどによる震えの場合は、様子が大きく異なります。呼びかけに反応しない、手足のピクつきが止まらない、顔色が悪い、口から泡を吹くなどの症状を伴うことがあります。
このような症状が見られる場合、特に初めてのけいれんであれば、迷わず救急要請をご検討ください。冷静に観察しながら、できるだけ早めに適切な対応を取ることが大切です。
子どもの熱が夕方や夜にだけ
上がるのはなぜ?
 風邪などの感染症では、夕方から夜だけ熱が上がることは珍しくありません。
風邪などの感染症では、夕方から夜だけ熱が上がることは珍しくありません。
もともと、私たちの体温は1日の中で変化しています。特に夕方から夜にかけては自然と体温が高くなる傾向があり、お子さまは体温調節が未熟なため、その変化がより大きく現れることがあります。
さらに、感染症時には体の中で炎症を抑えようとするホルモンや炎症物質の影響によって、夕方〜夜に熱が上がることがよくあります。
夕方や夜だけの発熱で、日中は元気に過ごせていて、ほかに気になる症状がなければ、まずは翌日の受診を検討しましょう。一方で、上記の症状を認める場合は医療機関を受診することをおすすめします。
発熱の主な原因と病気
発熱を伴う主な病気をご紹介します。
風邪
ほとんどがウイルス感染によって発症します。発熱、のどの痛み・咳、鼻水・鼻づまり、頭痛などの症状を伴います。また、腹痛や下痢が見られることもあります。水分をしっかりとり、安静にしましょう。
インフルエンザ
突然の高熱、倦怠感、のどの痛み・咳、頭痛、関節痛・筋肉痛などの症状を伴います。重症化すると、肺炎や脳炎などを合併するため注意が必要です。発熱から48時間以内であれば、抗インフルエンザ薬の投与が症状の改善に有効とされています。まれに異常行動を伴うこともあるため、解熱するまでは目を離さず慎重に見守りましょう。生後6か月以上のお子さまには、毎年のワクチン接種が推奨されています。
肺炎・気管支炎
風邪やインフルエンザなどのウイルス感染が悪化すると、肺や気管支に炎症が広がり、肺炎や気管支炎を引き起こすことがあります。発熱、しつこい咳、痰、胸の痛み、呼吸時のゼイゼイ・ヒューヒューといった音(喘鳴)が見られることがあります。特に呼吸が苦しそうな場合は、早めに受診しましょう。
溶連菌感染症
のどの細菌感染で最も多い原因菌です。発熱、のどの痛みとともに、のどの奥に白っぽい膿や舌にいちごのようなブツブツがみられることがあります。細菌感染症なので抗菌薬による治療が必要です。抗菌薬開始から24時間経過して、発熱などの症状が改善していれば登園・登校可能です。
アデノウイルス感染症(咽頭結膜炎)
アデノウイルスの感染により、38℃以上の高熱、のどの痛みや腫れ、頭痛、腹痛、下痢などの症状が引き起こされます。目にも感染しやすく、目の充血・目やにを伴う場合はプール熱と呼ばれます。治療薬はなく対症療法を行います。感染力が強く、熱が治まっても2日間は登園・登校ができません。
ヘルパンギーナ
ウイルス感染によって発症する、いわゆる「夏かぜ」と言われる病気です。口の中に水泡ができ、突然の高熱、のどの痛みを伴います。お熱は1~3日程度続くことが多く、のどの痛みが強い時は、食べ物を飲み込むことができなくなることもあります。治療は熱さましやのどの痛みを抑える薬を飲みむなどの対症療法となります。熱が下がり、食事や水分がしっかりとれるようになれば登園・登校が可能です。
水ぼうそう
水痘・帯状疱疹ウイルスの感染により、全身に小さな水ぶくれ(水疱)が現れる病気です。水ぶくれは頭皮にも見られます。症状が強い場合は抗ウイルス薬(飲み薬)を使用することがあります。発疹が全てかさぶたになるまでは、他の人に感染させる可能性があるため登園・登校はできません。かさぶたができるまでは通常5~7日程度かかります。感染力が強いため、定期予防接種がとても大切です。
はしか(麻疹)
麻疹は非常に感染力の強いウイルス感染症で、免疫がない場合は同じ空間にいるだけで感染することがあります。高熱に続き、咳、鼻水、目の充血、発疹などの症状が現れます。中耳炎、肺炎、脳炎などの重い合併症を引き起こすこともあります。予防にはワクチン接種が非常に有効です。
川崎病
川崎病は、全身の血管に炎症が起こる原因不明の病気です。高熱が続くほか、目の充血、唇や舌の赤み(いちご舌)、発疹、手足のむくみ、首のリンパ節の腫れなどの症状が見られます。重症化すると心臓の血管(冠動脈)に炎症や動脈瘤が起こることがあり、注意が必要です。これらの症状が見られた場合は、できるだけ早く小児科を受診し、入院のうえでの精密検査や治療が必要になることがあります。
発熱時の対処法
安静にする
体力が消耗しないよう、ゆっくりと休ませてあげましょう。日中に元気であっても、夕方から夜にかけて熱が上がりやすいため、十分に休ませて体力の回復を助けてあげることが大切です。
小まめな水分補給
発熱、下痢、嘔吐といった症状は、身体の水分を失う原因となります。いつもより小まめに水分補給をしてください。授乳中のお子さまの場合は母乳・ミルクを、離乳食を食べているお子さまの場合は経口補水液やスポーツドリンクをあげましょう。
水を飲めない、尿が少ない場合は脱水が疑われます。すぐに受診してください。
体温の上がり始めは身体を
温める・上がり切ったら熱を
逃がす
体温の上がり始め、寒気を感じるあいだは身体を温め、免疫機能を助けましょう。
逆に、体温が十分に上がり、汗をかき始めたり暑がるようになった場合は、衣類を調整したり、室温を下げたりして、体内にこもった熱を放出する工夫が重要です。首、わき、脚の付け根を冷やすのも良いでしょう。
解熱剤を使用する
発熱によって眠れない、辛そうな場合は、市販の解熱剤(子ども用)を使用しても構いません。
一方で、発熱があっても元気でよく眠れるようでしたら、解熱剤を使用する必要はありません。
よくあるご質問
発熱がある時、室温や湿度はどれくらいにすればよいでしょうか?
発熱時は、過度に温めすぎたり冷やしすぎたりする必要はありません。普段通りの快適な室温を保ちましょう。冬であれば20~25℃、夏であれば27~28℃を目安に調整すると良いでしょう。湿度は50~60%が理想で、乾燥していると呼吸器症状が悪化することもあるため、加湿器や濡れタオルなどで調整しましょう。
昨晩、発熱がありましたが、今朝になると下がっていました。登園・登校させてよいでしょうか?
熱は夕方から夜にかけてまた上がることが多いので、念のためおうちでゆっくり休むことをおすすめします。1日を通して平熱が続き、元気に過ごせていれば、登園・登校を再開しても大丈夫です。
解熱剤を使っても、熱が下がりません。受診した方がよいでしょうか?
熱の出始めは、解熱剤が効きにくいことがあります。お子さんの場合、熱が少し下がるだけでも元気が戻ることがあります。また、解熱剤で一度熱が下がっても、6時間くらいでまた上がってくることはよくあります。解熱剤は熱を一時的に下げるお薬なので、効き目が切れると再び熱が出てきます。水分がとれなかったり、ぐったりしてつらそうな時は受診をおすすめします。一方で、お熱があっても水分がとれていて、眠れているようなら、おうちで様子を見ても大丈夫です。
発熱がある時、お風呂はどうすればよいでしょうか?
お湯に浸かると体力を消耗するため、シャワーで済ませるようにしてください。お尻だけシャワーをして、あとは身体を拭いてあげるという方法でも構いません。熱が下がり、元気になれば、お湯に浸かっても問題ありません。